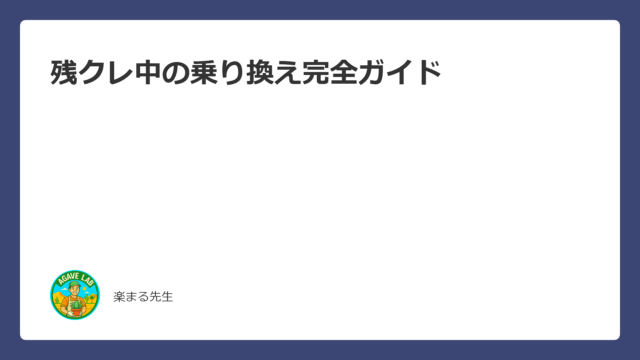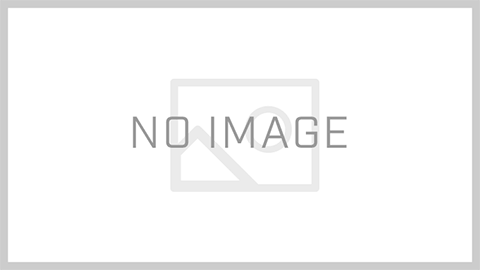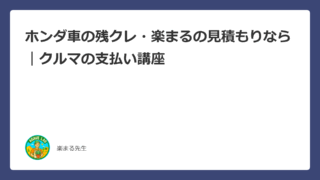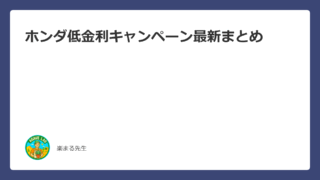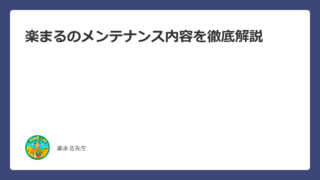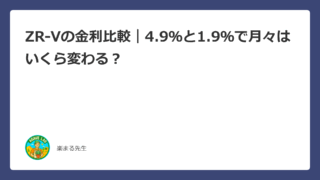N-BOXに「もっと手軽に乗りたい」と考えている方に朗報です。ホンダの楽まるプランなら、頭金なしで月額37,637円からN-BOXの新車に乗ることができます。
しかし、楽まるには独特の仕組みや注意点があり、契約前にしっかり理解しておかないと後悔する可能性があります。この記事では、N-BOX楽まるプランの詳細から契約条件、実際のメリット・デメリットまで包括的に解説します。
N-BOX楽まるプランの基本情報
ホンダの「楽らくまるごとプラン(通称:楽まる)」は、車両代・税金・メンテナンス費用がすべて含まれた定額制のカーリースサービスです。一方で、従来の残価設定型ローン(残クレ)とは根本的に仕組みが異なります。
つまり、楽まるは「車を借りる」サービスであり、契約期間中の所有者はホンダファイナンスとなります。さらに、月々の支払いが一定のため、家計管理がしやすいのが大きな特徴です。
| 項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 対象車種 | N-BOX(全グレード対応) |
| 車両価格 | 1,739,100円(標準グレード) |
| 契約期間 | 5年間固定 |
| 走行距離制限 | 月1,000km(年間12,000km) |
| 設定残価 | 727,260円(約42%) |
| 月額料金 | 37,637円(頭金0円時) |
ただし、上記の金額は標準的なケースです。まず、グレードやオプション、地域によって月額料金は変動します。次に、頭金を入れることで月額を下げることも可能です。
楽まるに含まれる費用とサービス
月額料金に含まれるもの
楽まるの月額料金には、一般的な車の維持費のほとんどが含まれています。具体的には以下の通りです。
- 車両代金(減価償却分)
- 自動車税(毎年の納税手続き不要)
- 重量税(車検時の支払い不要)
- 自賠責保険料
- 定期点検・車検費用
- オイル交換などの基本メンテナンス
- 延長保証(メーカー保証終了後も安心)
一方で、任意保険料とガソリン代は含まれていません。つまり、これらの費用は別途負担する必要があります。さらに、指定以外の整備工場での修理や改造は契約違反となる場合があります。
メンテナンス内容の詳細
楽まるのメンテナンスパックは非常に充実しています。まず、法定点検はすべてホンダディーラーで実施されるため、品質面での安心感があります。
ただし、メンテナンス時期の管理や予約は契約者が行う必要があります。また、指定外の部品使用や改造は保証対象外となるため注意が必要です。
契約満了時の5つの選択肢
楽まるの大きな魅力は、5年後の選択肢が豊富なことです。しかし、それぞれの選択肢にはメリット・デメリットがあるため、契約前に理解しておくことが重要です。
①新車への乗り換え
最も人気の高い選択肢です。まず、新しいモデルや別の車種に乗り換えることができます。次に、楽まるを継続することで、再度頭金なしでの契約も可能です。
②車両返却(残価保証あり)
車を返却して契約終了する方法です。つまり、残価分の支払い義務がなくなります。ただし、走行距離超過や車両状態によっては追加精算が発生する場合があります。
③残価での買取り
気に入った車を自分のものにしたい場合の選択肢です。さらに、727,260円の残価を支払うことで完全に所有権を移転できます。
④再リース契約
同じ車でリース契約を延長する方法です。一方で、月額料金は車両の状態や市場価値によって再計算されます。
⑤条件達成でそのままもらえる
特定の条件を満たした場合、追加料金なしで車がもらえるケースがあります。ただし、この選択肢は限定的で、詳細な条件はディーラーに確認が必要です。
楽まるの5つのメリット
①頭金なしで即納車可能
楽まる最大の魅力は、まとまった資金がなくても新車に乗れることです。まず、頭金・ボーナス払いなしで契約できます。次に、審査通過後は比較的早期に納車されます。
つまり、貯金を崩すことなく、月々の定額支払いだけで新車ライフをスタートできます。
②家計管理がしやすい定額制
楽まるは文字通り「定額」のため、家計の予算立てが非常に楽になります。一方で、従来の車購入では税金や車検費用が不定期に発生し、家計を圧迫することがありました。
しかし、楽まるなら毎月37,637円の固定費として計上でき、長期的な資金計画が立てやすくなります。
③充実したメンテナンスとサポート
楽まるには手厚いメンテナンスパッケージが標準装備されています。さらに、万が一の故障時もディーラーでの修理が基本となるため、安心感があります。
つまり、車に詳しくない方でも、プロのサポートを受けながら安心してカーライフを楽しめます。
④税金・諸費用の支払い手続きが不要
自動車税や重量税の支払いは、すべてホンダファイナンスが代行します。まず、毎年5月の自動車税納付書が届く煩わしさから解放されます。次に、車検時の重量税支払いも不要です。
ただし、任意保険の契約・更新は自身で行う必要があります。
⑤契約満了後の選択肢が豊富
前述の通り、5年後に5つの選択肢から最適なものを選べます。つまり、ライフステージの変化に合わせて柔軟に対応できるのが楽まるの魅力です。
楽まるの注意点とデメリット
楽まるにも無視できないデメリットが存在します。まず、契約前にこれらの注意点を十分理解しておくことが重要です。
①中途解約時の解約金
楽まるは5年間の契約が前提のため、途中解約には高額な解約金が発生します。つまり、転勤や家族構成の変化で車が不要になっても、簡単には解約できません。
解約金の計算は複雑で、残リース料・事務手数料・車両査定額などを総合的に勘案します。さらに、解約のタイミングが早いほど解約金は高額になる傾向があります。
②走行距離制限の存在
楽まるには月1,000km(年間12,000km)の走行距離制限があります。一方で、超過した場合は1kmあたり6円の追加料金が発生します。
つまり、長距離通勤や頻繁な遠出をする方は、事前に年間走行距離を慎重に見積もる必要があります。
③車両の改造・カスタマイズ制限
楽まるでは、車両の改造やカスタマイズが基本的に禁止されています。まず、エアロパーツの取り付けやローダウンは契約違反となります。
ただし、ホンダ純正オプションについては取り付け可能な場合が多いため、ディーラーに相談してみましょう。
④総支払額が高くなる可能性
楽まるの5年間総支払額は約226万円(37,637円×60回)となります。一方で、同じN-BOXを現金一括購入した場合は174万円程度です。
つまり、利便性と引き換えに、約50万円程度の追加コストが発生する計算になります。
楽まるがおすすめな人・おすすめしない人
楽まるがおすすめな人
初期費用を抑えたい方
頭金やボーナス払いなしで新車に乗りたい
家計管理を重視する方
毎月の固定費として車の支出を管理したい
メンテナンスの手間を省きたい方
車の知識がなく、プロに任せたい
楽まるをおすすめしない人
一方で、以下のような方には楽まるは向いていません。まず、車の改造やカスタマイズを楽しみたい方は制約が多すぎます。次に、年間走行距離が12,000kmを大幅に超える方は追加料金が発生します。
さらに、総支払額を最小限に抑えたい方は、現金購入や低金利ローンを検討した方が良いでしょう。
他の支払い方法との比較
N-BOXの購入方法は楽まる以外にも複数あります。つまり、それぞれの特徴を理解して、自分に最適な方法を選ぶことが重要です。
| 支払い方法 | 月額目安 | 総支払額 | メンテナンス | 所有権 |
|---|---|---|---|---|
| 楽まる | 37,637円 | 約226万円 | 込み | なし |
| 残クレ | 約28,000円 | 約200万円 | 別途 | あり |
| 一般ローン | 約30,000円 | 約180万円 | 別途 | あり |
| 現金購入 | – | 約174万円 | 別途 | あり |
ただし、メンテナンス費用や税金を含めた実質的な負担額で比較すると、楽まるの優位性がより明確になります。
契約手続きと審査のポイント
楽まるの契約には審査があります。まず、安定した収入があることが基本条件です。次に、過去の信用情報に問題がないことも重要です。
審査に必要な書類は以下の通りです。
- 運転免許証
つまり、事前にこれらの書類を準備しておけば、スムーズに手続きを進められます。さらに、審査結果は通常1〜3営業日で回答されます。
よくある質問(FAQ)
楽まるの途中解約は可能ですか?
はい、途中解約は可能ですが、解約金が発生します。解約金は残リース料や車両査定額によって計算され、契約期間の早い段階での解約ほど高額になります。転勤や家族構成の変化など、やむを得ない事情がある場合は、まずディーラーに相談することをおすすめします。ただし、解約を前提とした契約は避け、5年間継続できるかを慎重に検討してから契約してください。
楽まるの月額料金以外にかかる費用はありますか?
はい、任意保険料とガソリン代は別途必要です。任意保険は車両保険への加入も必須となります。また、走行距離が月1,000kmを超えた場合は、超過分について1kmあたり6円の追加料金が発生します。さらに、指定外の整備や改造を行った場合、契約満了時に原状回復費用を請求される可能性があります。これらの費用も含めて総コストを計算することが大切です。
楽まると残クレはどちらがお得ですか?
総支払額だけを比較すると残クレの方が安くなりますが、メンテナンス費用や税金の管理を含めて考えると楽まるにもメリットがあります。楽まるは定額制で家計管理がしやすく、突発的な車検費用や修理費用の心配がありません。一方、残クレは車の所有権があり、改造やカスタマイズも可能です。どちらを選ぶかは、総コストよりも利便性やライフスタイルを重視するかによって決まります。詳細な比較検討をしてから決めることをおすすめします。